はい。1人で考え出すと止まらなくなる「ねこにん先生」です。
考えながら歩いていると、「あれ?いつの間にここまで歩いたんだっけ・・・」と思うことがたま~にあります。みなさんは気を付けて歩いてくださいね。
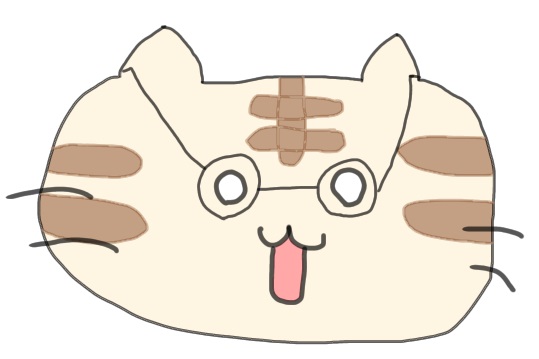
さて、今回はOECD(経済協力開発機構)が書いている「世界に学ぶミニ・パブリックス: くじ引きと熟議による民主主義のつくりかた(学芸出版社)」を読んでわかったことを紹介します。
「くじ引きと熟議」ってなんだろう?なんか面白そう!と思い、手に取りました。
では、はじめていきましょう!
どんな本なの?
初めに本の紹介です。
世界に学ぶミニ・パブリックス: くじ引きと熟議による民主主義のつくりかた
著者:OECD(経済協力開発機構) Open Government Unit
発売日:2023/4/29
出版社:学芸出版社
単行本:240ページ
まずおもしろいのは、この本を書いているのがOECD(経済協力開発機構) という組織(そしき)なところですよね。OECD(経済協力開発機構) とは、どうすれば世界全体の経済(けいざい)がよくなるのか考え、活動を行ってくれている国際機関(こくさいきかん)です。
そんな世界的な組織が、世界で広がっている「ミニ・パブリックス」というものの決め方について、メリットからそのやり方、注意すべき点まで説明してくれています。
ミニ・パブリックスについて学びたい方はもちろん、ものの決め方などで悩(なや)んでいる方にもアイデアとして新しい気づきがある本だと思います。
新しい世界(学び)
ミニ・パブリックスとは、「無作為(むさくい)」に選ばれた人が集まって「熟議(じゅくぎ)」を行い政策(せいさく)などを決めていくやり方のことです。
このままではわかりにくいですよね。
まずは「熟議」。これは熟慮(じゅくりょ)と討議(とうぎ)を繰り返すこと。ようするに、集まった人でじっくりと考えた意見をしっかりと話し合うってことですね。
次に、「無作為」。これは何も考えないでくらいの意味でしょう。本のタイトルも「くじ引き」と表されていますね(笑)
では、なぜ無作為に選ばれた人が決めることがよい方法なのでしょうか?
それは、公平(こうへい)だからだと思います。
例えば、学校で何か決めるときに「学校全体から選んだ10人」で決めるとします。
では、その10人がすべて男子だったらどうでしょう?
男子にうれしいことが決まりそうですね。
高学年の生徒が多かったら?
これも高学年にうれしいことが決まって、それ以外の学年にはあまりうれしくないかもしれません。
もちろんすべてがそうなるわけではないですが、どうしても不公平な感じを受けてしまいます。
なので、選ばれる人は何も考えずにくじ引きで決めてしまう。
そして、その選ばれた人でしっかりと考えて話し合う。このようにして決まったことだから、全体の意思決定として公平で、みんなのためになると考えられるのですね。
今回の授業はこれまで!ありがとにゃ。


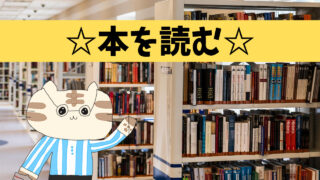

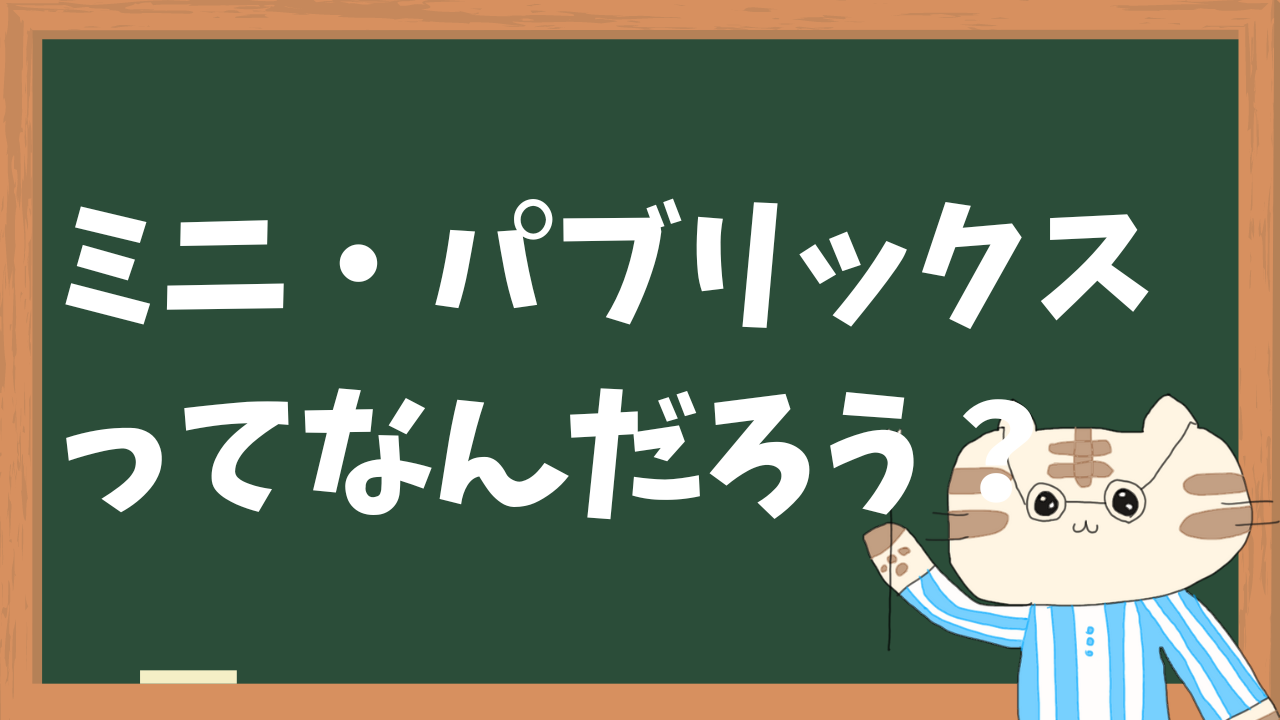
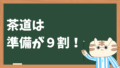
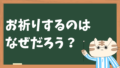
コメント